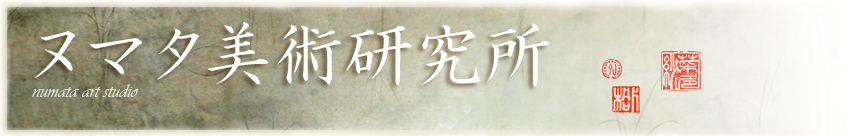上焼(じょうやち)
 | |
| 壺屋19C前半 沖縄県立博物館 図録「沖縄のやきもの」より |
歴史的には、17世紀後半に施釉陶器の技術が導入されたと考えられており、中国南部の灰釉碗を模した灰釉碗が最初期のものと言われています。1609年の薩摩による琉球侵攻、1644年には明の滅亡、清朝支配など、東アジア激動の時代にあって、独特の琉球文化が形成されていきます。喫茶文化も時代を反映し、江戸の茶の湯に、中国茶も嗜むことが求められ、双方の道具類が生産されています。
また、1724年当時の名工致元が八重山へ赴くなど、磁器の生産が探求されます。中国や古伊万里などのような磁器はないものの、湧田古窯や八重山古窯の灰釉陶器の中には、李朝陶器の堅手を彷彿とさせる趣の半磁質のものも見受けられます。更に1682年の壺屋統合以降更、 施釉陶器は、琉球独特の器種と共に多彩な技法と装飾を展開していきます。
また上焼という呼称は、壺屋製陶器に限って用いられることもありますが、ここでは壺屋に限らず湧田古陶など琉球陶器全般にわたり、施釉陶器(荒焼のマンガン釉を除く)は上焼と表わすこととします。